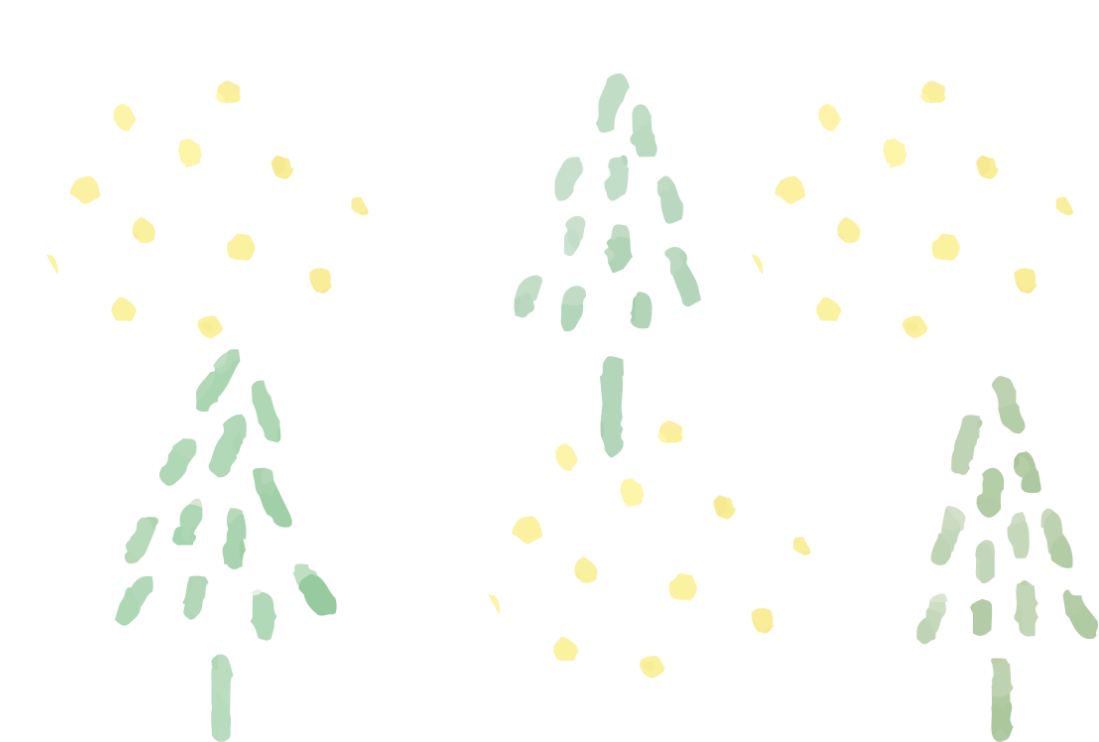州浜と箱庭

日本箱庭療法学会に参加して、『州浜論』の著者・原瑠璃彦先生の講演「日本の心の原風景の系譜-州浜から箱庭へ」を拝聴してまいりました。「州浜」と「箱庭(療法)」に共通するところがあるのではないかということで、今回のシンポジウムが企画されたそうです。
「州浜」と聞くと和菓子を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。「州浜」とは、曲線を描きながら出入りする海辺を指します。海と陸が直線的に分けられるのではなく、曲がりくねり、入り組んでいるところが、その本質であるとのお話でした。
ただし、「州浜」とは、人の手が加えられた人工的な風景に対してのみ用いられる言葉で、自然の風景には用いられません。
この「洲浜」という言葉が見られるようになったのは平安時代の歌合の記録が最も古く、そこで詠まれる歌の情景を表現するために「州浜台」という作り物が登場したそうです。これは、脚付きの台の上に砂や歌にちなんだ物を飾って表現されるもので、「箱庭」に通じるものといえるでしょう。
「州浜台」は、歌の世界をミニチュアで表す「箱庭」のようなものと考えられます。どちらも、小さな空間に内的世界を「見立てる」という点が共通しています。
「見立てる」とは、比喩の一種で、あるものを別のものと見なすことを意味します。子どものごっこ遊びや、落語家が扇子を箸に見立てること、枯山水では小石で水の流れを表現するなど、古来から私たちは「見立てる」ことを日常的に行ってきました。
箱庭療法は、砂の入った箱に中にミニチュアを自由に配置して自分の内的世界を表現します。箱庭を作るクライアントと、箱庭作品に込められたメッセージを受け取るカウンセラーが対話しながら心の動きやテーマについて理解を深めて行く、この過程においても「見立てる」力が発揮されていると思います。
話すことに抵抗がありカウンセリングに足が向かないという方は、一度、箱庭を作りにいらしてみませんか。自分自身と向き合うことで、新たな気付きが得られると思います。