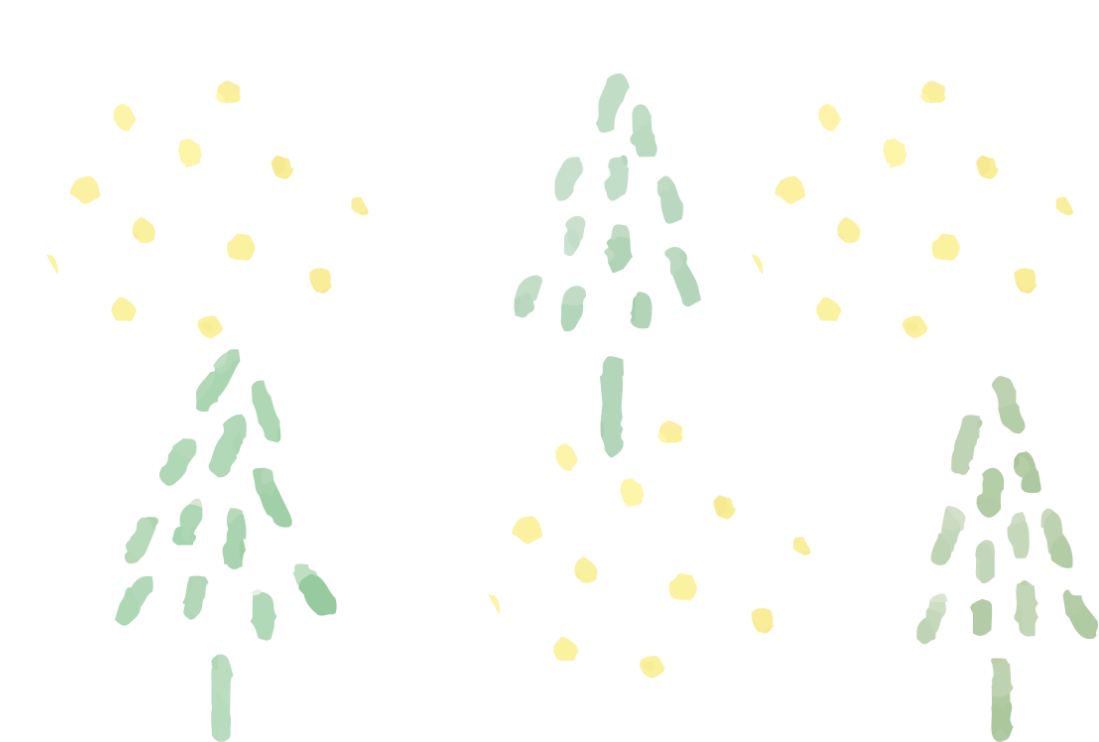秋の七草

暑さが長引いた今年も、ようやく秋の気配が感じられるようになってきました。
ところで、秋にも「七草」があることはご存じでしょうか。七草というと、「春の七草」を連想される方が多いのではないかと思います。春の七草は、1月7日に七草粥を食べて一年の無病息災を祈るものであり、またお正月料理などで疲れた胃を休めるためとも言われ、現代でもその時期になるとスーパーなどの店頭に並ぶのを目にすることも多いかもしれません。
春の七草は七草粥に用いられるように、実用性と季節の節目の意味合いが強いのに対し、秋の七草は秋の野山を愛でる文化そのものを象徴していると考えられ、鑑賞重視となっています。春の七草が食べて楽しむものなら、秋の七草は見て楽しむもの。野に咲く花々を愛でる、風流な文化です。そして、その由来は、万葉集に収められている山上憶良の二首の歌が元になっているとされています。
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびおり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花
萩の花 尾花 葛花 なでしこの 花をみなへし また藤袴 朝顔の花
現在の秋の七草は、萩(はぎ)、尾花(すすき)、葛(くず)、撫子(なでしこ)、女郎花(おみなえし)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききょう)の七つです。山上憶良の歌で「朝顔」とあるのは、諸説はありますが、桔梗のことを指すという説が有力となっています。
野山に咲く美しい花を観賞し、季節を感じて親しむことが秋の七草の目的です。そして、秋の七草に挙げられた植物は、食用ではないものの、薬草として古くから用いられてきたものが含まれていて、目で見る癒しとしてだけでなく、夏の疲れを実際に癒す役割も担って来たとも考えらます。
また、今でも秋のお月見、中秋の名月にはすすきを飾りますが、昔はすすきだけでなく、他の七草も飾っていたのだそうです。お月見のお供え物の定番としては、すすきの他に月見団子が馴染み深いですが、月が満ちた姿を模した丸い団子は、豊作への祈りや感謝の気持ちが込められているとされます。
現代では、月を眺める時間もなかなか取れず、お店に並ぶ月見団子や月見バーガーなどの商品で季節を感じることが多くなりました。それでも、ふと空を見上げて月の美しさに心を留める瞬間は、忙しい日々の中でほっとするひとときになるかもしれません。
今年の中秋の名月は10月6日ですが、その日を過ぎても、空気が澄んで月が一番美しく見えるというこの時季は、刻々と姿を変えていく月も楽しめるのではないでしょうか。お月見のお供に、秋の七草のうちいくつかを飾ってみるのも素敵です。野に咲く花々と月の光に心を寄せながら、秋の風情を静かに味わってみるのもよいかもしれません。